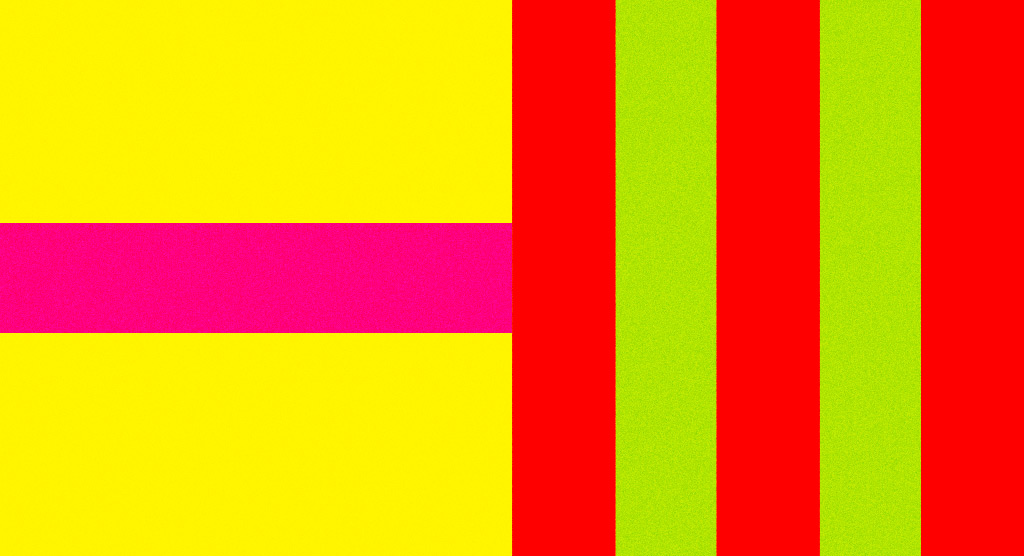出会いはいつも唐突に訪れる。
テェーンエイジャー中期の頃、同級生T君の家にお呼ばれした。兄貴の蔵書が興味深いので一緒に探索しようと。不在の兄さんの部屋に忍び込み、ベッドの下、バレバレに隠されてる成年誌など回し読みしていると、一冊の月刊誌が目に留まった。
水着のお姉さんが表紙の「アパッチ」という雑誌。タイトル上には「エンタテイメントの野生派」なるキャッチフレーズが謳われている。巻頭の野生派グラビアなど興味深くめくっていくと、見開きのモノクロページに手が止まった。見出しは『今、英国ロンドンでとんでもないエロチックバンドが大旋風』(ほぼ正確)。情報がなかったのか、内容はいい加減な三文記事だったが、演奏写真に釘付けになった。
見開きいっぱいにレイアウトされた粒子の荒い写真の真ん中で、髪を逆立て、目を見開きながらマイクスタンドにかぶりついているボーカルの男。上半身裸の痩身ベーシストは極限までストラップを下げている。弾けるのかそれで?
それまで洋楽はビートルズやクイーンなど、NHKで放映OKなミュージシャンしか馴染みがなかった。そんな純朴な青年にとって、そのグループの姿態は、バンド名と共に強烈なインパクトをもたらした。まだ一度も楽曲を聴いていないのに。
その名は「セックス・ピストルズ」。
彼らはエロチックバンドではなかった(どのようなバンドをそう呼ぶのか知らないが)。程なくして購入したアルバム『Never Mind the Bollocks』はそれまで聴いてきたどの音楽とも違った。PUNKムーブメントの背景など知る由もなかったが、ノーフューチャーなメッセージをぶちまけるジョニー・ロットンの雄叫びは、破天荒でひたすらカッコよかった。今でも一番好きなバンド名は?と聞かれたらセックス・ピストルズと即答する。
ピストルズ体験以降、音楽的視野が爆発的に広がった。当初はパンクロックに傾倒し、片っ端から過激な音源を探し求めていた。クラッシュ、ダムド、ストラングラーズ・・。ピストルズが突然解散し、パンクが終焉をむかえニューウェーブに道を譲ったころ、ロンドンから遠く離れたTOKIOで摩訶不思議な音楽が聞こえてきた。イエロー・マジック・オーケストラが出現したのだ。
テクノポップはパンク脳をあっという間に侵食し、気がついたらテクノカットになっていた。パンク愛聴仲間からは裏切り者呼ばわりされたが仕方がない。既成を壊すという意味ではテクノもパンク。そして当たり前のようにバンドを結成した。我々はテクノポップを演るのだ。
しかし、ひとつ問題があった。テクノポップを奏でるためにはシンセサイザーという高額な演奏機器が必要だった。キーボード担当は実家が農家のS君だった。メンバーの心配をよそに彼は名器YAMAHA CS-30を手に入れた。親父さんが大切に育てていた仔牛の花子を売って資金を調達したらしい。かわいい花子がシンセサイザーに化けた。
練習はもっぱらベース担当のY君の自宅で行なった。フェンダージャズベース、ストラトキャスター、最新シンセサイザー、楽器だけは一流。自分はドラム担当なのだが、もちろんドラムセットなど用意できない。部屋にあった少年ジャンプをガムテープでぐるぐる巻きにして擬似ドラムセットを組み上げ、セッションに参加する。高校生バンドのドラム担当はいつも情けなかった。
バンド結成時にはYMOが起爆となって、多くのテクノバンドが発生していた。プラスチックス、P-MODEL、ヒカシュー・・。メンバー全員で片っ端から聴き倒しコピーしていたころ、学園祭で講堂を公開するという噂を聞きつけた。通っていた高校はミッション系の男子校で、いつもは神聖な儀式にしか使用していなかった講堂を、音楽演奏などに使っても良いという英断が下されたのだ。演るしかない。
高校3年生バンドの最初で最後の晴れ舞台。出演者は先着順とのことだったが、我々のバンドはまだ名前がなかった。散々悩んで提案したバンド名は満場一致で即決した。
その名は「好色一団」。
当時、YMOのライブアルバム「公的抑圧 ~Public Pressure~」が発売されたばかりでその四文字漢字タイトルに触発された。メンバー全員けっして好色ではない好青年ばかりだったのだが、少し過激に自己主張したいお年頃だった。
意気揚々と出演登録をすませ、本番に向けてスタジオ練習を開始した矢先、教頭に呼び出しをくらった。「君たちのグループは参加を認めない」という通告だった。神聖なる場所で行われ、PTAも来場する催しもので、こんな破廉恥なバンド名はまかりならんということらしい。
ここは強行突破するしかない。校長室へ直談判しに向かった。校長先生は北欧から来た神父さんで、あまり日本語が得意ではなかったが、「好色一団」というバンド名は決して破廉恥なものでない!というまるで説得力のない主張を切に訴えた。優しい表情で話しを聞いてくれた校長先生は、おそらく意味不明のまま「インジャナイデスカ」と出演をあっさり認めてくれた。
学園祭当日、会場は超満員。好色一団のセットリストは、YMO「ライディーン」、シーナ&ザ・ロケッツ「ユー・メイ・ドリーム」、P-MODEL「ヘルス・エンジェル」。そしてなぜかシャネルズ「ランナウェイ」。仲良し4人組が俺らも混ぜてくれといってきたのでゲストに加えた。
「ヘルス・エンジェル」では代役ドラマーを立てボーカルをとった。スポットライトを浴びて観客席はまるで見えないが、客席の人熱は全身に伝わってくる。ドラム担当は全く練習してこなかったので演奏はボロボロだったが、大観衆の中、精一杯でかい声で歌う快感と高揚は今でも覚えている。生まれ変わったらミュージシャンになるしかない。好色一団はこのステージを最後に散開した。
YMOとの邂逅は音楽体験以上に大きな意味があった。今、デザインを生業としているのは、彼らとの出会いがあったからだ。ジャケットデザイン、ファッション、カルチャー誌、漫画、文学。テクノポップ誕生を起点に派生していったサブカルチャーは、いつも新しいデザインと共にあり、行く末を決定づける刺激と知見に満ちていた。ミュージシャンの夢は早々に諦めたが、YMOとの出会いはデザイナーの道に繋がっていた。
上京しデザイナーになったばかりの頃、YMOのメンバーに接近遭遇したことがある。
細野さんとは行きつけの本屋で並んで立ち読みした。六本木の青山ブックセンターでデザイン本を貪り読んでいたら隣の蛍光色スニーカーが目に入り、カッコいいなと見上げたら御大がそこにいた。あんなに緊張した立ち読みは未だ経験がない。
ユキヒロさんには道案内をした。深夜の仕事帰り、一方通行の路地に迷い込んだ黄色いポルシェがノロリと近づいて来た。窓が開いて「あの〜」と声をかけられた。僕のドラムのお父さんだった。
近くにミュージシャン御用達の隠れ家バーがあった。そこを教えてくれと。平静を装って淡々と車を誘導し別れ際「どうもありがとう」と言葉をもらった。
それはこちらの想いだった。僕が今ここにいるのは、あなたと出会ったからなのです。
高橋幸宏さんが病床にあるという。ゆっくりでもいいからしっかりと回復してほしい。
そしてまた、あのタイトなドラムスを聴かせてほしい。
心からそう願っています。